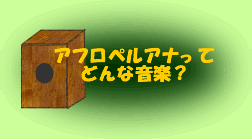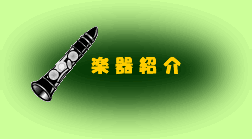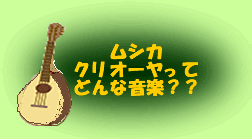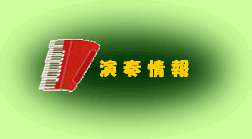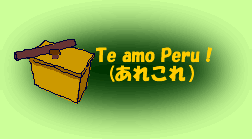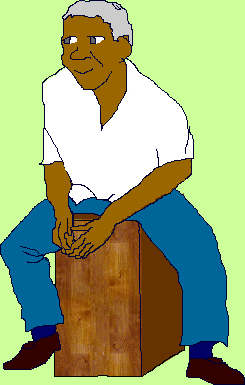

第185回ペルー共和国
独立記念日祝賀祭典
クリオーヤ音楽レビュー
毎年新木場で開催されていたペルーの独立記念日を祝う大イベントは、今年は例外的に横浜のBLITZで開催されました。好天のもと、ペルー人を中心とするラテン系、日本人、その他外国人も含めて2000人を超える来場者があり、14時から始まったイベントは熱く燃え上がりました。残念だったのは、メイン会場以外のスペースがあまりに少なく、会場としては少々不満が残る場所となりました。
このイベントは、私が関東にやってきた一昨年には、終わった直後にその存在を知って歯がゆい思いをし、去年初めて遊びに行きました。特にクリオーヤ音楽については、日本でこれほどクリオーヤ音楽を熱く聴くことができる場があり得たのか?というのが何にも増して衝撃でした。今年は二度目ということもあり、もっともっとリラックスして余裕をもって聴くことができました。昨年は、ブラジルや沖縄民謡、アンデス音楽など様々な楽団が雑多に参加していましたが、今年はアルベルト城間、ハラナ・クリオーヤを演奏するロス・デ・アフエラ、サルサのオルケスタ・コンキスタンド、それから今流行りのレゲトンバンド、グルーポ・ロス・カリブレスの四団体に厳選し、それぞれをたっぷり聴かせ、踊らせる、という趣向になっていました。
全体の大まかなプログラムとしては以下の通り。
14:00 開場
14:30 セレモニー
ペルー国歌斉唱/エクトル・マタジャナ総領事あいさつ
14:30 アルベルト・城間 ステージ
15:00 ハラナ・クリオーヤ (ペルーの黒人音楽。歌と踊り)
グループ名「グルーポ・ロス・デ・アフエラ(GRUPO LOS DE AFUERA)」
17:00 サルサ
グループ名「オルケスタ・コンキスタンド(Orquesta CONQUISTANDO)」
レゲトン
グループ名「グルーポ・ロス・カリブレス(Grupo LOS KALIBRES)」
20:00 終了

さて、私たちが会場入りしたのは13時45分ぐらい。会場はそろそろ人が増えてき始め、すでに混沌とした様相でした。まずは腹ごしらえと会場の脇に特設の野外屋台空間へ。今年の会場はこの野外空間が異常に狭く、さらに人でごった返しており、食べ物を買っても食べるスペースがほぼない。しかたなく、地べたに座ってヤンキーの様にむさぼり食う(笑)。
とりあえずの空腹感を満たしたあと、いざ、会場の中へ・・・と思うと、私は知り合いにばったり出会い、その知り合いの友人たちとそのまましばし歓談。私が今連載している「音楽三昧 ペルーな日々」などへの好意的な感想をいただきました。
話しているうちに会場ではすでにセレモニーが始まっていたので大急ぎで中へ。会場ではちょうど皆が起立して国歌を斉唱しているところでした。熱気を帯びたような厳粛な空気が会場に漂う。遠く、祖国を離れて生きる人々にとって、こうした大きな会場で祖国の国歌を同胞と共有するかけがえのない時間。異邦人には立ち入れない、ただ敬意でもって応えることしかできない時間だ。
続くペルー領事の日秘友好をより促進していかねばならない的な挨拶を経て、いよいよイベントが開幕。司会の仰々しい大げさなMCの中、アルベルト・"ベト"・城間が登場。日系ペルー人などの間でも大きな人気があるのか、大歓声があがっていました。彼は日本ではどうも沖縄系のイメージが一般的に強いようだが、やっぱりラテン人であることは隠せない。インティ・ライミを意識したのか「太陽の祭り」というタイトルのアンデス的なサウンドを織り込んだなかなか好感度の高い曲なども演奏。バルスをギター一本で聴かせたり、その音楽の幅の広さと持ち前の勢いでお客を大いに沸かせました。残念なのは、後半カホン奏者のマリオ・カストロを加えたが、音響バランスが悪く(二階席にいたためか?)、カホンの音がほとんど聴こえなかったこと。

曲は初っぱなから強烈なマリネラ・リメーニャ。リマ風のマリネラという意味ですが、八分の六拍子のギターとカホンにあわせてハンカチを持ったペアが踊る19世紀後半に大流行したフィエスタのための音楽です。よく通る声で朗々と歌いあげるグスタボ・ヨナミネの歌のパンチに、カルロスとエリカのエレガンテな踊りがさっそうと映えます。最近はペルーでもマリネラといえば北部のマリネラ・ノルテーニャ人気が強く、リメーニャ離れが進んでいるイメージが強かっただけに、初っぱなからマリネラ・リメーニャから始まったのは非常に印象的でした。マリネラ・リメーニャは、後半によりテンションをあげていくレスバローサ、フーガという部分を伴うので、他の地域のマリネラ以上にスリリングで、否応なしに心をかきたてられる。大きな拍手と歓声が会場に響きわたりました。
続いて歌手がマリア・エレナ・デ・アソシーナに交代し、昨年末になくなった日系ペルー人作曲家、ドン・ルイス・アベラルド・ヌニェス・タカハシ氏のもっとも有名なバルスの一曲、マル・パソが高らかに歌いあげられました。アベラルド・ヌニェスは、ペルーのクリオーヤ音楽界でも一、二を争うほど代表的な作曲家であり、五十年以上名曲を作り続けた偉人です。10年ほど前から子供たちの日本移住にあわせて日本に移住し、愛知県で生活しながら作曲活動を続けていました。晩年になっても精力的に作曲活動を続け、その数は数百に登っていました。その中でもっとも有名な曲の一つがマル・パソです。ペルー人ならほとんどの人が口ずさめる、そんな一曲だ。そのほかにもマリアエレナによるバルス(ペルー風ワルツ歌謡)数曲とポルカが歌われました。ポルカは20世紀前半頃までは非常にペルーでも人気の高かった大衆音楽で、フィエスタの花形の一つでした。景気のよいリズムと歌詞にあわせて激しく踊りまくる音楽でしたが、黒人音楽が盛んになるに従って、徐々に踊られなくなって行きます。ちなみにペルーでは、サッカーの応援歌としても重要な地位を占めています。
続いて、愛知からチャロ・ウンテン女史が登場し、アベラルド・ヌニェスのバルスを高らかに歌いあげました。実は今回のハラナ・クリオーヤの企画として、昨年なくなった偉大な日系人作曲家を追悼する演奏会という意味合いも込められていました。チャロさんとは今年5月に愛知県豊田市で行われたアベラルド・ヌニェス追悼公演でも一緒でしたが、5月はフォーマルな衣装に身を包みむしろ厳かな雰囲気で歌っていたのに対し、今回は派手な衣装ではじけまくっていて、そのギャップになにより驚かされました。5月にはアベラルド・ヌニェスに捧げるバルスを歌っていただけあり、独立祭でもアベラルド・ヌニェスの曲を歌い、その後、ペルー賛歌である「イ・セジャマ・ペルー(そして、その名はペルー)」を会場を巻き込んで熱唱。貫祿を見せつけました。
チャロさんの次は、今回が初めての大舞台という若手歌手、ディアナ・ヒガ。慣れぬステージに多少の戸惑いも見せつつ、有名なバルス「ヨ・ペルディ・エル・コラソン」を熱唱。その歌唱力に会場も大いに盛り上がりました。
そのあと、歌手は再び始めにマリネラを熱唱したグスタボに戻り、これまた代表的なバルスから「アルマ・コラソン・イ・ビダ」を歌いました。「魂はあなたを征服するために、心はあなたを欲するために、そして命はあなたと共に生きるためにある」という熱烈な愛のバルスです。そして、アベラルド・ヌニェス作曲のペルー贊歌「アルコ・イリス(虹))」も続けて歌いました。彼の晩年もっともお気に入りだったバルスの一曲で、私にとっても昨年、生前の彼に会った時に教えてもらった想い出の曲でもあります。バルスの中ではそれほどまだ有名にはなっていませんが、なかなかどうしていい曲です。ただ、他の曲に比べ、伴奏者の不慣れが少々目立ってしまう結果となってしまっていました。
次に登場したのは、若手男性歌手のコニ・ハシミネ。わたしがしびれるほど好きな「セ・アカボ・イ・プント」を熱唱。この曲もペルー・バルスを代表する作曲家、フェリックス・パサチェの傑作です。「私たちの愛は死んだ。全て終わった。これからどうしようか。ああ、人生なんてこんなもんだ」と愛の終わりを熱く、切なく歌いあげます。
次の女性二人は、ユリコ&トミコ・ロリ。これまたコテコテバルスの名曲「ハマス・インペディラス」と「ドンデ・トゥ・バヤ」を歌いました。バルスには、故郷贊歌も多いですが、何といっても愛を歌うための音楽としてその真価を発揮します。「ハマス・インペディラス」は、ペルー・クリオーヤ最高の歌手の一人であり、絶頂期に夭折したルーニャ・レジェスの代表曲の一つ。そして、「ドンデ・トゥ・バヤ」は、ペルー北部の王女と称されたマリッツァ・ロドリゲスの代表曲の一つです。共に愛に生きる女性の心を熱く歌いこんだ名曲です。
こうしたバルスの名曲中の名曲が目白押しで歌われると、それだけでももうクラクラしてきます。一曲一曲が持つ音楽のエネルギーに翻弄されてしまいます。そうして最高のタイミングで再び初っぱなに登場したマリネラ・リメーニャが再び登場。歌手はやはりグスタボ。カルロスとエリカの優雅でスタイリッシュな踊りが華麗に舞い、会場はますます熱く、熱く沸き上がります。
そこでいよいよ満を持してアフロペルアナの登場。司会の黒人セルソ・イジェスカスがギターの伴奏にあわせてコプラ(四行詩)を吟唱し、黒人ダンサー二人のサパテオ(タップダンス)の試合が繰り広げられました。これは、相手のステップとは異なるリズムで互いに複雑なステップを繰り広げて足技の優劣を競うものです。超絶的なサパテオに会場が大きく沸きます。
そのまま、ステージでは黒人ダンサーがフェステホのリズムにあわせての即興の踊りを繰り広げていきました。そして客席でひときわ激しく踊っていた我等が友人ホルヘさんの娘さん、ハナエ・フロールにお声がかかり、ステージに引っ張りあげて、セルソと二人で濃厚なフェステホの踊りを見せつけるように踊りまくりました。会場は二人の熱く激しい踊りに大盛り上がり。
そして、日本人にも親しみやすい「蛍の光」をフューチャーしたフェステホ「ヒピ・ハイ」に突入します。ヒピ・ハイはペルーでもお別れ前にかかる音楽で、ロス・デ・アフエラのフィエスタもいよいよクライマックスであることを否応なしに実感させます。しかし、いつもいつも思わされるが、フェステホに蛍の光をこんなにかっこよく乗せるなんて、普通の感性ではとてもできることではありません。
ヒピ・ハイに続いてはこれまた現代フェステホの決定版とも言えるエバ・アイジョンの「エストイ・エナモラーダ・デ・ミ・パイス(わたしは祖国の恋人」。ステージにはこれまで登場した歌手や踊り手たちが勢ぞろいし、順番にフェステホを踊るなどして会場を沸かせます。やっぱり、歌手も歌だけでなく、きっちり踊りも踊れるところ、そういうところがこの音楽の一番重要なところです。歌って、当然のように踊れる。それに尽きます。
そうしてみなでフェステホを踊りまわし、セルソのメンバー紹介とともに最後の曲へと流れ込みます。最後の曲は、フェステホよりさらにスピードの速いインガーという赤ちゃんを抱いて踊るアフロ系の踊りでした。インガーという名前は、赤ちゃんの泣き声から来たというからおもしろい。ステージなどでは人形の赤ちゃんを抱いて踊ることが多いというが、わたしは残念ながらまだ見たことがありません。
そんなこんなで、大盛り上がりの中、クリオーヤ音楽のハラナ・クリオーヤの時間は幕を閉じました。会場の転換の間には当日の入場券を使ったくじ引きが行われ、会場が大きく沸いていました。いつも思うことですが、特にラテン系のMCほど胸躍るMCはないように思います。ドラマティックに熱く語る彼らに、そうした語り口を忘れてしまった日本を少し寂しく思いつつ、会場脇で愛知から来たチャロさんやアベラルド・ヌニェスの娘さんのマリさんなどと挨拶し、ひとときの時間を過ごしました。
そこで踊りを踊っていたエリカとカルロスにばったり出会い、カルロスと今度食べに行く計画をしているペルー料理屋の話や今日のコンサート、そしてカルロスたちが次に踊る予定にしているイベントなどの話で盛り上がり、ちょこっとメレンゲを踊り、家族で来ていたホルヘさんと歓談しているうちにサルサは終わりいつの間にやらレゲトンが会場では始まっていました。会場内を映したモニター越しに初めて見る(聴いたことはあっても踊りを見たのは初めて)レゲトンにおののきながら(笑)、さらにしばらく話をして午後七時ごろ、横浜ブリッツを後にしました。
せっかくだから、ということで、ペニャハメンバーでそのまま川崎で途中下車して川崎の有名なペルー料理レストラン、インティ・ライミに行き、その絶品な料理に舌鼓を打って帰途につきました。
← トップへ